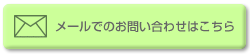ここ2週間ほどの間にメロンを食した後、瞼や唇が腫れて来たといって来院されるケースが重なりました。
あきらかにメロンを食べた後の反応ですので、食事性アレルギーそのものです。
バラ科の果実であるリンゴ、モモ、ナシ、イチゴ、サクランボ
ウリ科の果実であるメロン、スイカ、キュウリ
バナナ、ジャガイモ
などでアレルギーがでることがあります。実は厳密には仮性アレルゲンといわれます。
通常アレルギー反応がでるとヒスタミン、ロイコトリエン、セロトニンという物質が体の中の細胞から飛び出し、そのために痒くなったり腫れたりするのです。
上記の食べ物はヒスタミンを多く含んでいるので、アレルギー時と同じ反応が出てしまうのです。
食べると喉がいがらっぽくなって咳がでたり、唇や顔面が腫れてきたり、時には嘔吐や下痢が出ることもあります。
本来アレルギー性体質がある場合は、これらの食べ物でより悪化することがあります。
一度上記の食べ物で反応が出た場合、その食材には十二分に注意してください。
また果実のアレルギーがある場合、人ではラテックス(ゴム)にも反応が出やすいそうです。
人の場合ですが
スギ花粉、ヒノキ花粉→トマト
シラカバ花粉→バラ科【リンゴ、モモ、サクランボ、ナシ、イチゴ、ウメなど】
キウイ、ニンジン、セロリ、クルミ
ブタクサ→スイカ、メロン、キュウリ、バナナ
カモガヤ→メロン、オレンジ、トマト、バナナ、セロリ、ジャガイモ
ヨモギ→リンゴ、キウイ、ニンジン、セロリ
これらにも交差反応するそうです。動物ではまだ明確に立証されていないようです。でも注意かが必要ですね。