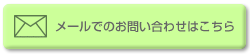春が過ぎると蚊のシーズンです。
家の中に蚊が侵入してきますと、蚊取り線香や殺虫剤噴霧が定番となる対処策です。
ところがアフリカ、東南アジアや中南米、ミクロネシア、ポリネシアに生息しているネッタイシマ蚊の7割が、殺虫剤の主成分であるペルメトリンに耐性を持つ遺伝子を持っていることが判ったそうです。
殺虫剤効かないネッタイシマカ、東南アジアで確認…日本に侵入しデング熱など媒介の恐れ : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
ネッタイシマ蚊はデング熱を媒介する昆虫で、現在日本では繁殖した記録はないそうですが、外国からの荷物や船、飛行機に紛れて侵入した際、予てからの温暖化により今後国内繁殖も確認される危惧があると言われております。
抗生物質、抗真菌剤、抗ウィルス剤、殺虫剤。
これらはとても有効で人類にとって必要不可欠な薬剤ですが、長きに亘って使い続けてきた結果、細菌、真菌(カビ)、ウィルス、虫などがそれに負けないような対応をしてきてしまい、次に効果のある薬剤を求めて研究は続くのでしょうが、イタチゴッコは否めません。
もっと根本的なところに戻って対応策を練る必要があります。これは薬剤を使ってきた私たちの責務でしょう。